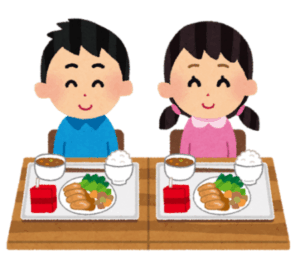豊渓中学校の統廃合計画の見直しを求める3件の陳情について 賛成の立場での討論
毎定例会では、その定例会中に出された陳情や議案について、本会議で最終的な採決の前に賛成・反対の理由や意見を述べる「討論」があります。今回、生活者ネットワークが討論に臨んだ豊渓中学校の統廃合問題についての討論内容を掲載します。
陳情第99号「保護者や地域との合意形成なしに豊渓中学校の統廃合を決定しないことを求めることについて」
陳情第104号「教育学的根拠が不十分な学校統廃合対象校の区独自選定基準の見直しについて」
陳情第105号「豊渓中学校を対象とした学校統廃合計画を見直し、地域の声の反映を求めることについて」
以上三件の願意に賛成の立場から討論
文部科学省は今年3月から「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議をこれまで6回開いています。その中で、国の調査で、全国の市区町村のうち、「おおむね適正規模である」と答えた自治体はわずか25%。残る75%は、何らかの課題があると認識していることが示されています。
その中で、委員の貞広斎子氏(千葉大学教育学部教授)は、「全てを解決するベストな学校規模は存在しない。地域特性や諸条件は様々であり、重要なのはサイズを変えることではなく、地域や教育行政が適切な方策を取れるかが問われている」と述べています。
さらに、委員の一人である秋田県五城目町職員による発表では、学校改築にあたり、町民全員が参加できる形で意見を交わす「スクールトーク」を、4年間で10回にわたり開催したと報告しています。回を重ねる中で、住民の議論は「校舎改築」そのものを越えて、「地域にとって学校とは何か」「子どもにどう育ってほしいか」「町がどんな未来を描くのか」という、より本質的な話し合いへと広がっていったとのことです。それが結果として、学校の枠を超えて、地域・世代・学びをつなぐ新しい学校のかたち、町民が誇る「越える学校」を生み出しました。
もちろん、全ての住民の思いが通ったわけではないでしょう。しかし、子どもたちと地域のために議論を尽くした経験は、地域の力を飛躍させていくものだと考えます。
一方、練馬区、豊渓中の場合はどうでしょうか。
まず、区は第二次実施計画案を示してから、当初は、ほんの3ヶ月ほどで計画を策定する予定でした。これでは最初から地域の声を聞く気がなく、地域の活動を軽視していたと言われても仕方がありません。
それを立証するかのように、学校と地域が、まさに「地域にとって学校とは何か」「子どもにどう育ってほしいか」を日々話し合いながら運営してきた学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の意見を、聞き入れていません。
この陳情を否決するということはそういうことです。
合意形成どころか、これまで旭町地域が積み重ねてきた活動を顧みない判断と言わざるを得ません。
この夏、私も中学生と同じ10キロ以上の荷物を持って旭町3丁目から光が丘第一中学校まで往復してみました。片道35分はかかります。区は自転車通学を可としましたが、保護者や地域の方が子どもたちの学びの場に足を運ぶことは少なくなるだろうと感じました。地域から学校をなくしていくということは、学校を中心に育まれてきた地域のつながりという財産をなくしていくことです。
また、子どもの権利の視点から、区は「施策を着実に実施することを通して、子どもの権利擁護を図っており、区条例を制定する考えはない」と言っていますが、今回に関しても、当事者である子どもの声を十分に聞いたとは言えません。
このようなやり方を容認すれば、今後も子どもの権利や地域を軽視した学校統廃合が進められかねません。
それは、地域の主体的な意識を削ぎ、住民が「何を言っても無駄」と感じる区政をつくってしまいます。
区長が掲げる「参加と協働を根幹に据えた区政運営」とは、ほど遠い状況だと言わざるを得ません。
以上のことから、陳情の願意に賛成し、討論を終わります。

豊渓中学校の統廃合計画の見直しを求める陳情に賛成の討論