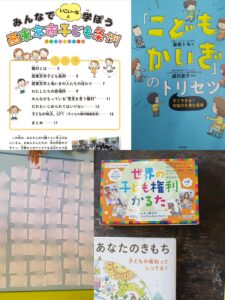練馬の学校給食の今
生活者ネットワークはこれまでも学校給食を有機給食(オーガニック給食)に!と働きかけてきました。私もそのバトンを受けついで活動しています。
私たちは遠くのものを莫大なエネルギーを使ってかき集め、環境負荷が高くコストも高い食材を使ってでも「オーガニック給食を!」と求めているのではありません。区内の生産者からは「ただ、オーガニックを求めるのではなく、作り手の想いや野菜の物語も知ってほしい」という声も。どのような形なら実現可能なのか。練馬区の学校給食と農産物の現状についての理解もさらに深めていく必要があると考えています。
<直近の練馬区の学校給食の状況を保健給食課に聞き取りました>
◯一食当たりの平均予算:小学生…低学年288円・中学年302円・高学年321円、中学生…全学年379円 ※今後も続く物価高を考慮しての予算立てをしている。年間約21億円(2024年より無償化)
◯ゲノム編集食品への考え方:使用しない
◯調味料:各学校に任せている
〇パン:学校給食会にて調達※大量に納品できる業者が限られているため。学校給食会が地域に工場がある業者を割り当てている。練馬は・東武パン・東和パンの2社(両方とも板橋の業者)小麦粉はアメリカ産と国産を使用。
〇麺類:学校給食会にて調達※宮原製麺・桜井商店(両方とも練馬区)
〇野菜:学校のまわりにある畑から採れた野菜等も取り入れている
〇魚・肉・果物・調味料など:各学校の栄養士にお任せしている ※契約は必ず複数の業者と契約し、欠品がないようにすること。さらに、そのうちの1事業者は区内業者にすることなどを決めている。どこを選ぶかは栄養士次第。学校給食会を利用していることが多い
〇洗剤:純石けん・合成洗剤は区の予算で一括購入。それ以外のものは業者の負担
〇食器:陶器のものを使用
<今現在の学校給食に有機農産物を取り入れる際の課題>
・量の問題:そもそも地場の農産物がたりない
・金銭面:コストがかかる
・運ぶ人がいない:地場の野菜を朝採って、洗って、各学校へどう届ける?
・大量発注の調整が困難(欠品は許されない。量をそろえること。その調整役が必要)現在その作業は学校の栄養士
・栄養士さんが超多忙(毎日座る暇なし) 練馬区では半数が都の職員、もう半分が会計年度任用職員であり、なかなか地元の農家さん複数人と密に連絡をとりあって進めることも困難?しかし、オーガニック給食をすすめるうえではコーディネーターが必要。
区は都市農業を推進しており、それを支えるためにいろいろな施策があり、各学校でも練馬の農業を伝える授業に取り組んでいます。練馬の小学生は「練馬大根」と「青首大根」の見分けもすぐにできるほど。練馬大根を使った「練馬スパゲティ」も人気です。年に5回は区内農産物を使った一斉給食を実施、それらを推進するための「食農連絡会議」もありますが、議事録公開なし・傍聴不可となっています。(区以外の事業者との会議体のためとのこと)私たちはこの会議ももっとオープンなものにできないか、流通の仕組みのさらなる工夫や、コーディネーターの設置など、議会の中で提案できることを考えています。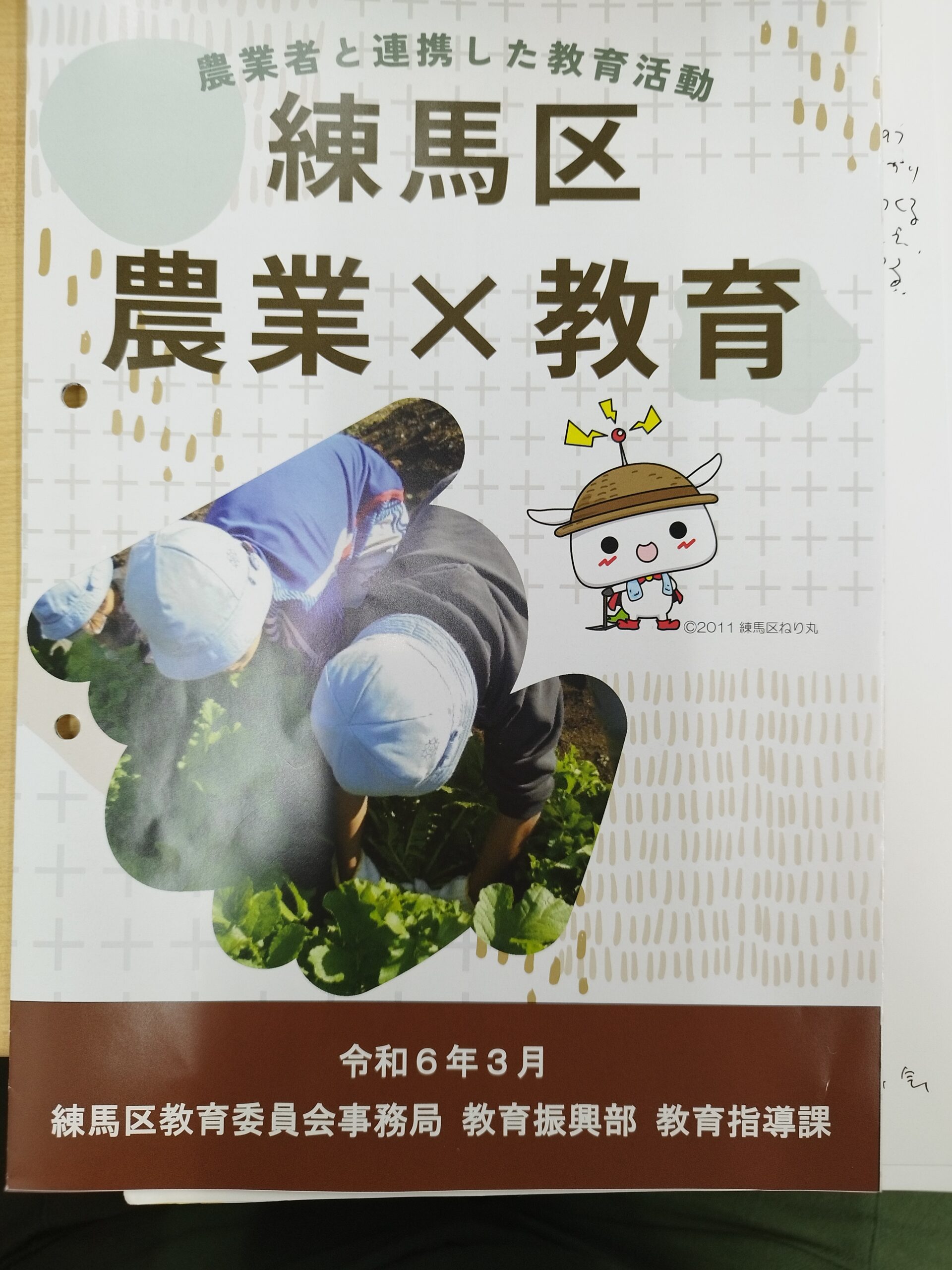
練馬区が行っている、学校で練馬の農業を伝える取り組み「有機給食スタートブック」の編著者である専修大学人間科学部教授の靍(つる)理恵子さんのお話をうかがう機会があったのですが、「想いを集めて仕組みをつくる、なければ作る!」「できることから始める」など心強い言葉が印象に残っています。生活者ネットワークはもともと「食の安全」等を求める市民運動から生まれた団体(45年前!)です。給食は国産利用を・遺伝子組み換え食品は使わないで!など、一歩一歩、少しずつ実現し、進めているところです。今後もみなさんからのご意見お待ちしています。一緒に実現していきましょう。
「オーガニック」という言葉について
「オーガニック」の野菜・食材をうたうには、認証制度や基準があり、それを取得するには事務手続きなどにもお金も労力もかかり、また慣行栽培とは間隔を空けて作付しなければならない、など様々な障壁があり、有機栽培、減農薬等に挑戦している生産者も「オーガニック」という言葉は使えずに、または使わずにいる方も多くいます。
そんな背景もあり、私たちは敢えて「オーガニック」という言葉を使わずに活動をしてきました。昨今、「オーガニック給食」を求める声は大きくなってきており、それは必ずしも「オーガニック認証」された給食という意味ではなく使用されていることから、私たちもより伝わりやすい表現・表記として「オーガニック給食」を、また「食とのつながりを知っていく活動」として捉え、使っています。
関連ブログ:「食とつながりなおす」活動!